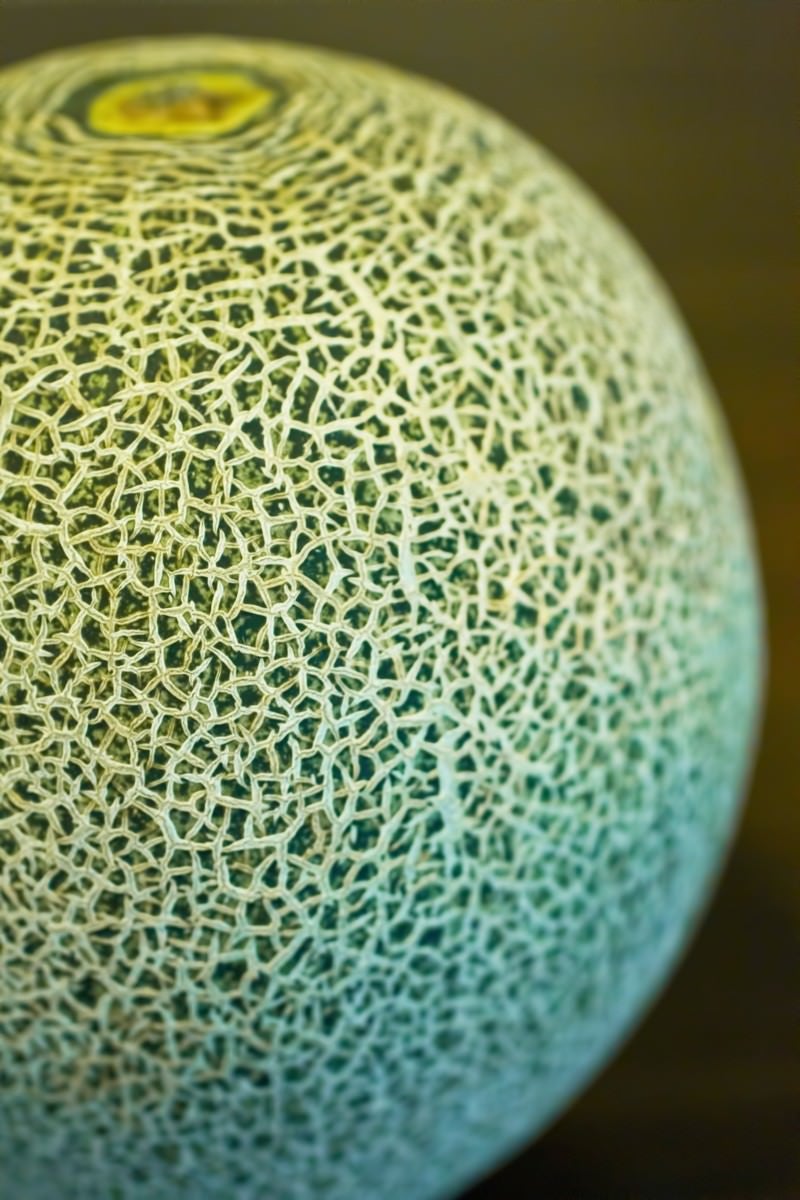なぜ衆議院解散で「万歳」するの?意味不明
おかしいという声に応える3つの理由と歴史的背景
衆議院が解散される際、議場で議員たちが一斉に「万歳!」と叫ぶ光景。
ニュースやSNSで見て、「え、クビになったのになんで喜んでるの?」
「失業したのに万歳って不謹慎じゃない?」
と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
実は、この「解散万歳」には深い歴史的背景と、
現代の政治家たちの複雑な心理が隠されています。
今回は、その理由を分かりやすく解説します!
1. なぜ解散で万歳するのか?3つの主な説
なぜ彼らは万歳をするのか、主に以下の3つの理由があると言われています。
① 天皇陛下への敬意(歴史的な慣習)
最も有力なのが、明治時代からの名残です。
衆議院の解散は、憲法に基づき天皇陛下の「詔書(しょうしょ)」によって行われます。
陛下からのお言葉を賜ったことに対し、
感謝と敬意を表して万歳をするようになったのが始まりとされています。
② 選挙への「出陣の勝鬨(かちどき)」
解散が決まった瞬間、議員たちは「前議員」となり、
すぐに選挙戦へ突入します。
これから始まる厳しい戦いに向けて、「絶対に勝つぞ!」という気合入れ、
つまり戦国時代の「エイエイオー!」のような意味合いで万歳をしています。
③ 緊張からの解放と「ヤケクソ」!?
いつ解散されるか分からない緊張状態から解き放たれ、
一種のトランス状態(興奮状態)で叫んでしまうという説もあります。
中には「もうどうにでもなれ!」というヤケクソな気持ちが混じっているという声も……。
2. 「おかしい」「意味がわからない」という批判の声
最近ではSNSを中心に、この慣習に対して否定的な意見も増えています。
国民感情とのズレ: 「物価高などで国民が苦しんでいるのに、議員が万歳して盛り上がっているのは違和感がある」
合理性の欠如: 「失業するのにお祝いするのは論理的におかしい」
実際に、若手議員の中には「慣習に合理性がない」として、
あえて万歳をせずに座ったままの姿勢を貫く人も出てきています。
3. まとめ:万歳は「日本の政治の伝統行事」
衆議院解散の万歳は、古い歴史からくる
**「儀式」と、選挙に向けた「景気づけ」**が合わさった日本独特の文化と言えます。
しかし、時代の変化とともに「古臭い」「理解できない」
という声が強まっているのも事実です。
次に解散のニュースを見る時は、どの議員が万歳をして、
どの議員がしていないか注目してみると、
今の政治の空気がより見えてくるかもしれません。